当社が携わる長い和装業界での経験とニット商品の企画生産の強みを背景に誕生いたしました。
着物と洋服のスタイルの境界線をなくし、民族や年代、スタイルの枠を飛び越えて、ファッションを愛する全ての人がその日その気分とスタイルでご使用いただけるスタイルレスなアイテムを提案いたします。
わたしたちは、創業より現在まで、和装、洋装、意匠撚糸、寝装、宝飾品など幅広い事業領域にわたって、常にお客様起点で商品を調達し、また製造して参りました。各事業の長年にわたり積み上げてきた伝統を探り、変わりゆく現代にあった新しい価値を創造して参ります。
当社は「私たちの使命は、伝統を探り、新しきを創造し、心豊かな社会の発展に貢献する」という理念のもと、SDGsに関わる取組みを通じて、持続可能な世界の実現に向けてより一層の努力を続けていきます。
「SDGs」とは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現させるための国際社会の共通目標です。アイコンで示される「17の目標」とそれぞれの具体的目標である「169のターゲット」、「244の指標」から構成されています。


着物でも洋服でも使える兼用アイテムで「物を増やさない」仕組みを提案するYOUTOWA、流行を追わないデザインと、100回洗えるタフさを持つ「長く使い続けられる」ニットを提案するUN-USELESS、サステナブルなモノ作りに取組み続けます。

当社が携わる長い和装業界での経験とニット商品の企画生産の強みを背景に誕生いたしました。
着物と洋服のスタイルの境界線をなくし、民族や年代、スタイルの枠を飛び越えて、ファッションを愛する全ての人がその日その気分とスタイルでご使用いただけるスタイルレスなアイテムを提案いたします。

“100年着てもへたれない洗えるタフなニット”
ファッション業界の課題であるサステナブルな物作りに対し、流行を追わず、長く着続けられ、年齢や性別も関係なく、家族やパートナーとも着回しの出来る、本当に必要とされる“unuseless=不要でない”商品を提案いたします。

当社では、持続可能な社会の実現に向けて、環境に配慮した素材や業務の省資源化に積極的に取り組んでいます。オーガニックコットンやBCIコットン、再生繊維など環境負荷の少ない素材を採用するほか、梱包資材の再利用によって廃棄物の削減に努めています。また、お客様に商品を長くご愛用いただけるよう、訪問時には草履の修理対応も行っています。さらに、契約書の電子化や請求書のデジタル送付を推進し、紙資源の削減と業務の効率化を図っています。社内では、デスクトップPCからノートPCへの移行を進めることで、消費電力の抑制と柔軟な働き方の実現にも寄与しています。




マテリアル事業部では2016年度より、ひとの健康と環境に優しいBCIコットンの使用を開始し、取引量の拡大につとめています。
ヘルスケア部では、ウレタン製品加工先との間で、梱包資材の再利用を繰り返し、ゴミの排出を減らす、環境に優しい取組みを行っております。
きもの事業部ではお得意先様へ出向いてお客様の出張修理を実施し、お気に入りの草履を少しでも長く大切に愛用して頂けるよう、環境に優しい取組みを行っております。
2024年10月からは、取引先との契約締結において電子契約システムを導入いたしました。
契約書作成・送付・保管における紙の使用量と印紙税をはじめとする関連コストの大幅な削減を達成するとともに、契約締結までのリードタイムを短縮し、業務効率の向上に寄与しております。

2025年2月より、請求書の発行を電子化することで、紙の使用量を削減し、郵送に伴うCO2排出量の抑制に貢献しております。

2024年7月より順次、従業員が利用するデスクトップPCを低消費電力のノートPCに切り替えました。この取り組みにより、オフィス全体の電力消費量を大幅に削減し、従業員の機動性を高め、多様な働き方に対応可能な環境を整備しました。

Our Valuesである「変革と挑戦」「多様性の尊重」「共創共栄」の実現のため、多様な人材を登用し、リスキリング支援や育児・介護等の両立支援制度を通じて、多様な人材が活躍できる職場の環境作りを推進します。


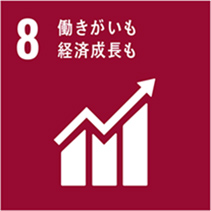


当社は、任意団体「work with Pride」が策定した企業や団体におけるLGBTQ+などのセクシャルマイノリティへの取組みの評価指標「PRIDE指標」において最高評価「ゴールド」を2024年11月14日に受賞いたしました。
当社のour value(私たちの価値観)のひとつに「多様性の尊重」があります。私たちは、マイノリティを排除するのではなく、それぞれの立場をよく知り、各々の「違い」を受入れ、認め合うことが大切であり、それが一人ひとりが持つ能力を最大限発揮することへとつながると考えております。
全従業員対象のLGBTQ研修後、LGBTQの支援者「ALLY(アライ)」であることを表明できるオリジナルステッカーを製作し、希望者に配布しております。
異性間・同性間にかかわらず、パートナーを配偶者、パートナーの子らを家族として扱えるよう規程を整備。慶弔見舞金、休暇付与等の人事制度、社員販売等の福利厚生を見直しました。パートナーシップの申請にあたっては、プライバシー保護のため、申請ルートも必要最低限の人数に限定しました。
社内相談窓口を設置。社内イントラネットで周知し、社内の当事者、管理者等からの問い合わせに対応できるようにしております。
経営層からダイバーシティに関する定期的なメッセージ発信、キャリア形成支援や働き方変革を通じた社員(管理職・従業員)の意識改革などに全社的かつ継続的に取り組んでおります。
公的・民間資格取得に関する補助制度
働き方に合わせた制度の見直しや創設
・フレックスタイム制度の導入
・テレワーク制度の導入
育児・介護の休業、休暇、時短勤務等の制度
経営層からダイバーシティに関する定期的なメッセージ発信、キャリア形成支援や働き方変革を通じた社員(管理職・従業員)の意識改革などに全社的かつ継続的に取り組んでおります。

サステナビリティに関する基本方針や重要課題の特定、さらには重要課題の監視・管理等のため、サステナビリティ関連のリスクと機会について分析し、対応策について検討を行ってまいります。
リスクと機会については、サステナビリティ委員会にて定期的に確認を行い、必要に応じて重要課題及びその指標や目標を見直すなど適切に対応してまいります。
| 【リスク】 | 【機会】 |
|---|---|
| ・流行を追わない・兼用アイテムなどの特性から、一部の価値観に共感する層にしか受け入れられない。 | ・環境意識の高い消費者や、ミニマリズム・エシカル消費に共感する層には強い支持を得られるためPOPUPなどによる販売機会の拡大。 |
| 【リスク】 | 【機会】 |
|---|---|
| ・請求書の電子化に伴い、情報漏えいやシステム障害によるトラブルが発生する可能性 ・新しい機器や働き方への移行に、従業員の教育・慣れが必要 |
・電子請求書の導入により、用紙・封筒・輸送エネルギーの削減が実現 ・ノートPCへの切り替えで、オフィス全体の電力消費量を恒常的に削減 ・ノートPC化によりテレワーク・フレキシブルワークが可能となり、人材確保や生産性向上 |
| 【リスク】 | 【機会】 |
|---|---|
| ・請求書の電子化に伴い、情報漏えいやシステム障害によるトラブルが発生する可能性 ・新しい機器や働き方への移行に、従業員の教育・慣れが必要 |
・電子請求書の導入により、用紙・封筒・輸送エネルギーの削減が実現 ・ノートPCへの切り替えで、オフィス全体の電力消費量を恒常的に削減 ・ノートPC化によりテレワーク・フレキシブルワークが可能となり、人材確保や生産性向上 |